お父さんと話しても、何も伝わってない気がする
映画『港に灯がともる』をテアトルで鑑賞しました。
阪神淡路大震災から30年経った、2025年1月17日に合わせて公開された本作。

大阪で暮らす私にとって、見逃せない作品だと感じていました。

こんなあらすじだよ。
1995年の震災で多くの家屋が焼失し、一面焼け野原となった神戸・長田。かつてそこに暮らしていた在日コリアン家族の下に生まれた灯(富田望生)。在日の自覚は薄く、被災の記憶もない灯は、父(甲本雅裕) や母 (麻生祐未) からこぼれる家族の歴史や震災当時の話が遠いものに感じられ、どこか孤独と 苛立ちを募らせている。一方、父は家族との衝突が絶えず、家にはいつも冷たい空気が流れていた。ある日、親戚の集まりで起きた口論によって、気持ちが昂り「全部しんどい」と吐き出す灯。そして、姉・美悠(伊藤万理華)が持ち出した 日本への帰化をめぐり、家族はさらに傾いていく――。なぜこの家族のもとに生まれてきたのか。家族とわたし、国籍とわたし。わたしはいったいどうしたいのだろうーー。
https://minatomo117.jp/
今回の記事では、映画の感想を交えつつ、阪神淡路大震災や日本における地震による災害などをお伝えしていこうと思います。
阪神淡路大震災
1995年1月17日、午前5時46分。日本の静かな朝は、突如として地獄のような光景に変わりました。マグニチュード7.3の巨大地震が兵庫県南部を襲い、阪神淡路大震災として歴史に刻まれることとなりました。この地震は、わずか20秒で都市を瓦礫の山に変え、6,434人の命を奪いました。
神戸市を中心に広がる被害は、まるで戦場のようでした。ビルは崩れ、道路は裂け、火災が発生し、街全体が炎に包まれました。電気、水道、ガスといったライフラインは寸断され、人々は暗闇と寒さの中で震えながら救助を待ちました。家族を失った悲しみと、家を失った絶望が交錯する中、被災者たちは互いに助け合いながら生き延びる術を見つけていきました。
地震の影響は、物理的な被害だけにとどまりませんでした。経済的な打撃も甚大で、多くの企業が倒産し、失業者が溢れました。特に神戸港は、日本の主要な貿易拠点としての機能を一時的に失い、国際的な物流にも大きな影響を及ぼしました。
しかし、絶望の中にも希望の光はありました。国内外からの支援が次々と寄せられ、ボランティアたちが被災地に駆けつけました。彼らの献身的な活動は、被災者たちにとって大きな励みとなり、復興への道のりを照らす灯火となりました。
復興は決して容易な道のりではありませんでした。瓦礫の撤去から始まり、インフラの再建、住宅の再建、そしてコミュニティの再生と、多くの課題が山積していました。しかし、被災者たちは決して諦めませんでした。彼らは互いに支え合い、未来への希望を胸に、一歩一歩前進していきました。
震災から30年が経過した今、神戸は再び活気を取り戻しています。新しいビルが立ち並び、かつての傷跡はほとんど見えなくなりました。しかし、震災の記憶は決して風化することなく、次世代へと語り継がれています。震災を乗り越えた人々の強さと絆は、今もなお神戸の街に息づいています。
阪神淡路大震災は、日本にとって忘れられない悲劇であり、同時に人々の絆と復興の力を示す象徴でもあります。この経験を通じて、私たちは自然の脅威に対する備えの重要性を再認識し、未来への希望を胸に、より強い社会を築いていくことを誓ったのです。
私と日本と地震
私がこれまで生きてきた期間には、阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本地震、能登半島地震など、多くの犠牲者を出した災害が発生しています。
上記のもの以外にも、日本は本当に地震が多い。気象庁のデータを見ると、ゾッとします。(https://www.data.jma.go.jp/eqev/data/higai/higai1996-new.html)
しかしながら、私は幸いなことに阪神淡路大震災の時は関西には住んでおらず、また、それ以外の地震についても、被災することはありませんでした。
地震発生の少し後に、大阪に帰ってきました。大阪では震災の少し後に、O-157集団食中毒も大変だったんですが、その騒ぎも特に経験することなく、事後に大阪へ戻ってきたんです。
時は経ち、2011年3月11日、当時私は大学生でした。大学の卒業旅行で海外に行ってたんです。日本が大混乱に陥る中、私は大学の仲間と飲んで騒いでいました。私が行った先でも、津波の危険があるということで、夜の街には出られないということになり、「なんだよ」と不満さえ飛ばしていました。海の向こうでは、事の深刻さが分かっていなかったのです。なんて不謹慎だったのだろうと猛省しています。
またしても私は、災害を自分事にすることができなかった。
それに加えて、東日本大震災の余震や悲しみが蔓延する中、社会人としての第一歩が始まってしまい、自分のことだけで精一杯。亡くなった方を追悼する心の余裕もありませんでした。
なので、今なお当時の自分の愚かさや冷たさに、反省する日々です。被災した人々に申し訳ない。そんな気持ちはずっと、心のどこかで疼いています。
こういうのも、一種のサバイバーズ・ギルトというらしいんです。
サバイバーズ・ギルト(suivivor’s guilt)とは、被災地で自分だけ生き残ったことで抱く罪悪感、あるいはそれに似た感情のことをいいます。東日本大震災においては、私のように被災地から離れた場所の人々にも、こういった気持ちは広がっていったそうです。
被災も何もしてない私がこんな気持ちを抱くこともおこがましいのかもしれませんが。
阪神淡路大震災から30年。30歳よりも若い人々は、この地震より後に生まれた世代になります。
『港に灯がともる』の主人公も、その世代の若者なんですね。
向き合い方と、伝え方と
本作で私が一番印象的だったセリフが、
「お父さんと話しても、何も伝わってない気がする」
というものです。
主人公の灯は、震災の直後に生まれた子で、父・母・姉と、その点で分かり合えないというコンプレックスを抱いています。さらに、彼女は早生まれで、同級生もほとんどが震災を経験しているということもそれに拍車をかけるんですね。
さらに、お母さんも「あんたが生まれた時大変やった」と悪気無く言ってしまったり、父親に至っては当時の出来事を怒りと悲しみを込めて伝えるばかり。
何も知らない自分は一体何なんだろう。生まれてきてよかったのかな。
そんなことを考えてしまっているわけです。
被災した人々の悲劇に共感できる人はたくさんいても、彼女のような知らないが故にたくさんのストレス、心の傷を負ってしまった人への共感というのは、これまでなかなかなかったんじゃないでしょうか。
加えて、在日であるというのも、この家族の人間関係をさらに複雑なものにさせているんです。
本作のお父さん、本当に伝え方が下手なんですよ。だから娘も聴きたくなくなってしまうんですね。
自分の心の弱いところには、触れたくないですもんね。お互いに。だから、伝え方っていうのは本当に大事だなと思います。
震災と在日であることが絡み合って、普通の昔話ができない。これでは家族はバラバラになってしまうでしょう。これも一つの被災だよなと思います。
楽しく親や子どもと昔話ができる。これも有難いことなのだと感謝しなければ。
本作で主演を演じた富田望生。彼女の出身は福島県いわき市。
東日本大震災が起きたとき、彼女は小学5年生だったそうです。家が半壊し、東京へ避難したそうですが、しばらくは「ふるさとを捨てたと思われているかもしれない」と罪悪感を抱き続けていたんだそうです。切なる演技が堂に入っていたように感じます。
今日の映学
最後までお読みいただきありがとうございます!
映画『港に灯がともる』について感想をお伝えしました。

震災が起こったことそのものの悲劇ではなく、知らない世代にもスポットをあてた考えさせられる作品です。

伝え方や聴き方って、大事だよね。
X(旧Twitter)はこちら
https://twitter.com/bit0tabi
Instagramはこちら
https://www.instagram.com/bit0tabi/
Facebookはこちら
https://www.facebook.com/bit0tabi/
noteはこちら
https://note.com/bit0tabi
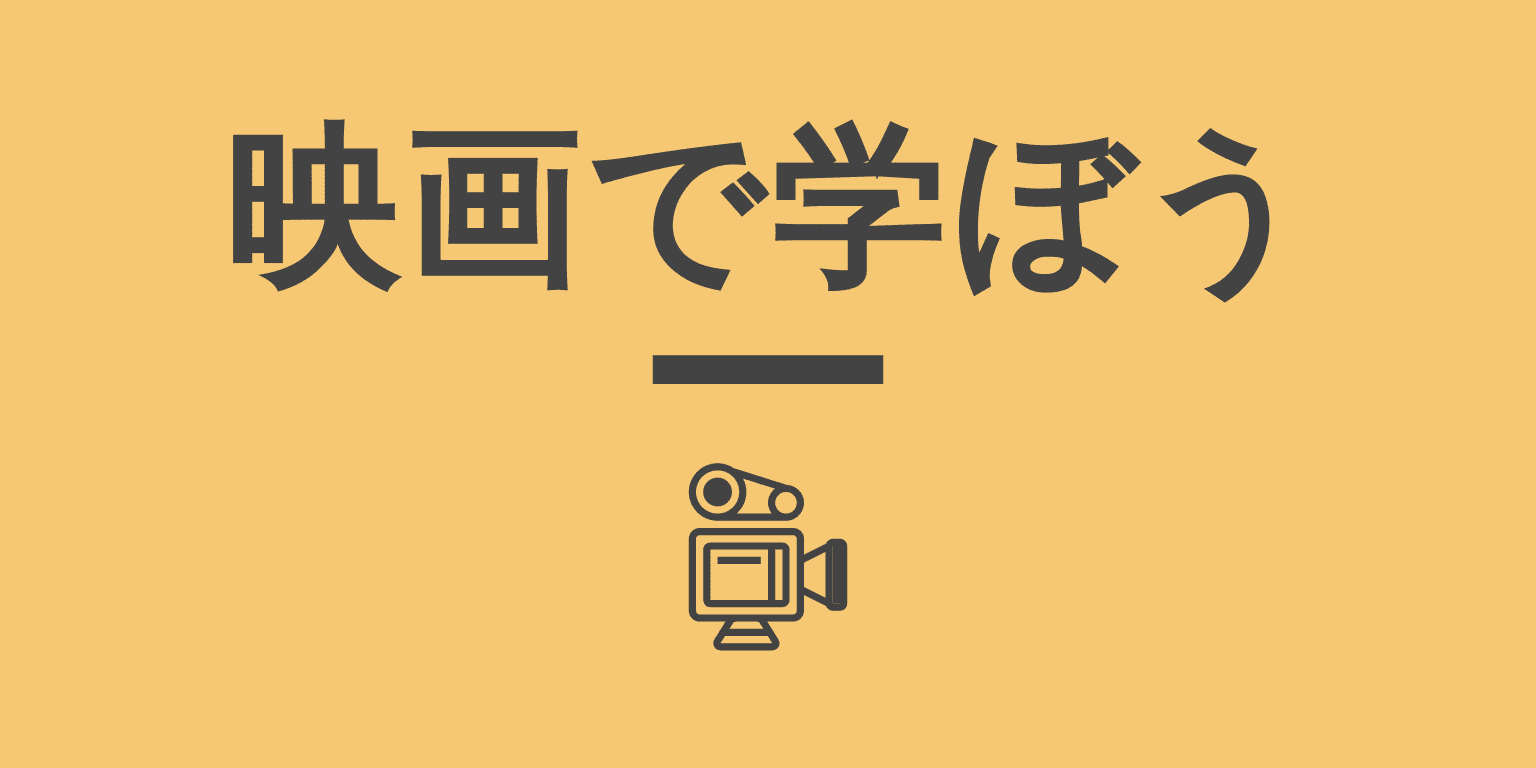



コメント